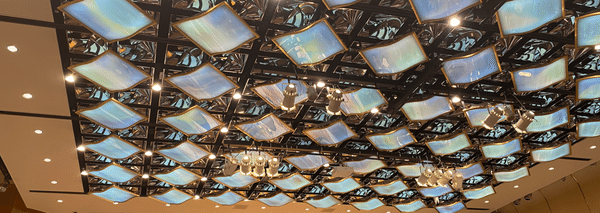山内宏泰 公式サイト
記事一覧
「若冲さん」 11 20211101
その日から四代目は紙に墨をのせ、鶏らしきかたちが浮かんできたかと思えばそれを反故にして、また新しい紙を取り出してきて墨をのせ、ということを延々と続けるようになった。
文字通りほかに脇目もふらず、日々、紙を浪費しまくった。しかも彼は、いい紙を惜しげなく使う。そこはさすが京都錦通りの大店である。四代目が自由に使っていい金子は豊富にあって、紙を買い込んでくることくらいわけもない。
伊藤家として
「若冲さん」 10 20211031
四代目さんはただの木偶の棒じゃなかったんだ、引き篭もり店主だの何だのと彼を馬鹿にしてきた連中の鼻面に、この絵を突きつけてとくと見せてやりたい。
とユウは思った。
しかも四代目は実物の鶏をチラと見ることもなく、スラスラとこの似姿を描いてしまった、ほとんど妖術使いみたいな芸当ができてしまうんだぞと、声を大にして主張したかった。
そう考えていたら、ユウは思い至った。そうか四代目さんは三年間ず
「若冲さん」 9 20211030
画材を大事そうに持ち帰ってきた四代目を見て、ユウは訝った。
これはいったい誰が使うものなのだろう。まさかご当人が?
彼が絵を描きたいだなどとは、ユウはまったく気づきもしなかった。彼はただ、鶏を見るのが好きな人としか思っていなかった。
よくよく教えを受けてきたのか、四代目は画材を手際よく片付け整頓した。
済むとさっそく紙を広げはじめた。早くも何か描くつもりか。
色とりどりの顔料にはま
「若冲さん」 8 20211029
丹波で豆を作っていた家を出て京都の大店・桝源へ奉公に入り、当主のお世話を仰せつかってはや三年余。ユウが顔貌に湛えていたあどけなさもすっかり消えたころ、仕えている四代目伊藤源左衛門が動いた。
庭のもみじの葉の色が最濃の盛りを過ぎた日の午後、四代目は大きな包みを両手でかかえて帰ってきた。ユウの眼にはその姿がいつになく、いそいそして浮き立っているように思えた。他の者はまず気づかないだろう微細な粟立
「若冲さん」 7 20211028
今日もユウは雑事をこなす合間に、縁側から庭の鶏を眺めやっている四代目の背中を、ちらちらと見た。
胡座に頬杖を突き背を丸めた四代目は、いつ眼を向けても身じろぎひとつしない。居眠り中かと見えるが、とんでもない。前方へ回れってみれば、だらしない姿勢に似合わず眼頭にはちゃんと力が入っており、眼球はチラチラよく動き、視覚が活発に働いていると知れる。
眼だけあまりに生き生きしているから、ユウには四代
「若冲さん」 6 20211027
ユウの憤慨をよそに、四代目自身はよくいえば悠々自適、悪くとれば無気力な引き篭もりを続けた。
時折り朝晩の食事をするとき愁いを湛えた目つきをするが、それが家の者たちから軽んじられているのを嘆いてのものか、それともほかの因があるのか、ユウには判別できなかった。
今日もまた陽が上るとともに朝食を済ました四代目は、障子越しに外気を見やって、
「いい日和だな」
とつぶやき、いそいそと鶏小屋の扉を